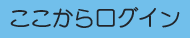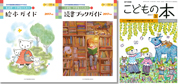百姓仕事の何を伝えるか
田植えの時につけた足跡にお玉杓子(オタマジャクシ)が集まっています。強い日差しの中で、少しでも水温が低いところを探しあてたのです。べつに私は彼らのために足跡をつけたわけではないのに、何となく嬉しくなります。田んぼの水だって、お玉杓子を育てるために溜めたのではありません。
このように、意図せず目的としていないのに、百姓仕事の結果として、生きものたちは生をくり返します。ありふれた自然現象です。百姓も、このことを言葉にして伝えたりはしません。
しかし農業の土台には、こういう百姓仕事の不思議さがあるからこそ、自然は輝き農業生産は持続してきたのです。なぜなら稲は米になる前に生きものとして、他の生きものたちと一緒に、こうした世界で育ってきたからです。
私たち百姓は、仕事の中で目を合わせる生きものには、つい言葉をかけてしまいます。「もう花を咲かせたね」「少し調子が悪いんじゃないか?」と。この生きもの同士のような感覚は、かつては、百姓の目指すところでした。「稲の声が聞こえるようにならないと一人前の百姓ではない」と言われていた頃を思い出します。
現代では、「こういう技術を行使すれば、こうした結果が得られます」というマニュアルが溢れています。しかし、相手の生きもの(作物・家畜・田畑)が「こうしてほしいと願っているから、こういう手入れをするんだ」という感覚こそが、農のいのちです。
案外子どもたちには、この感覚がよく伝わります。大人が抱かなくなった疑問を、子どもはぶつけてきます。「土に石ころがないのはなぜ」「なぜ赤とんぼは人間に寄ってくるの」と。それに私は百姓の「語り」で答えます。
じつは子どもたちに伝えたかったことは、大人にも伝えたいことでした。これまで誰も語ろうとしなかったことが、小林敏也さんのたおやかな絵にのって、きっとあなたをうなずかせることでしょう。
(うね・ゆたか)●既刊に『農は過去と未来をつなぐ』『日本人にとって自然とはなにか』など。

農山漁村文化協会
『うねゆたかの 田んぼの絵本(全5巻)』
宇根 豊・作/小林敏也・絵
各巻定価2,970円(税込)/揃定価14,850円(税込)