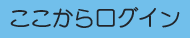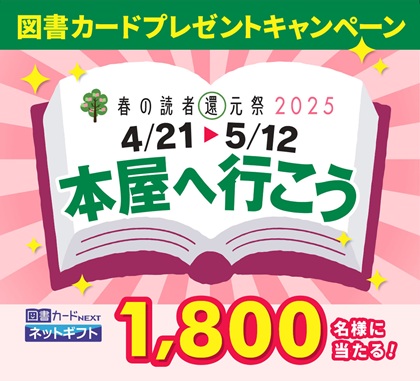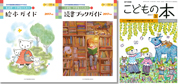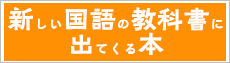研究することの面白さを伝えたい
本書の目的は、博士課程のときにおこなった、岡山県におけるニホンウナギの調査研究の紹介を通じて、読者の方々に生き物を研究することの面白さをお伝えすることにある。
たとえば本書には、ウナギとアナゴの関係について紹介しているくだりがある。同じ場所に住んで、同じ種類のエサを食べているのに、実際には食べるエサの大きさが異なっているために、両者はエサをめぐる競争の関係にはないという研究結果である。調査地である岡山県の児島湾では、ウナギとアナゴが喧嘩せずに仲良く暮らしていたのだ。両者が仲良く暮らすための仕組みはとうぜん、研究を始める以前から存在していたはずだ。しかし、この研究でウナギやアナゴの分布、サイズ、活動時間、胃の内容物などを調べたことによって、初めてその存在を知ることができた。
児島湾におけるウナギとアナゴの関係のように、生き物やそれを取り巻く環境の中には、人間の目には見えない、さまざまな仕組みがある。この仕組みは、我々人間がその内容を知ろうが知るまいが、そんなことには全く関係なく存在している。しかし、適切な方法を使って研究することによって、目に見える形に浮かび上がらせることができる。これこそが、生き物の研究のもっとも面白い部分だろう。手法の重要性を伝えるために、本書では調査研究から得られた結果だけでなく、研究手法についても詳しく説明した。
もうひとつ、研究対象であるウナギをめぐる現状についても、なるべく分かりやすくお伝えすることを心がけた。なぜウナギは減っているのか、いまウナギのために何をするべきなのか。ウナギの問題について考えるために必要な基本的な情報とともに、この問題を多面的に捉えるための視点を紹介している。
本書を手にした読者が、生き物を研究することの面白さを少しでも感じてくれれば、さらに、食資源について、水辺の環境について自ら考えるきっかけになれば、これほど嬉しいことはない。
(かいふ・けんぞう)●既刊に『ウナギの博物誌』『うな丼の未来 ウナギの持続的利用は可能か』(いずれも分担執筆)。
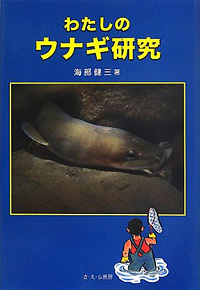
さ・え・ら書房
『わたしのウナギ研究』
海部健三・著
本体1,300円