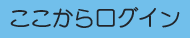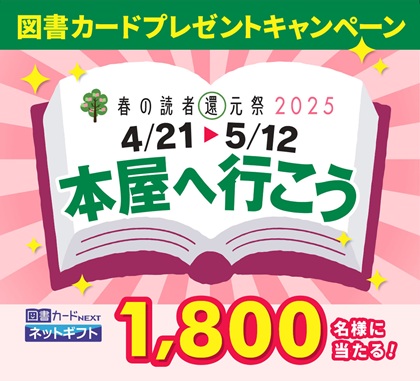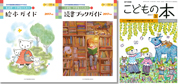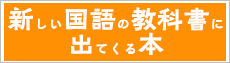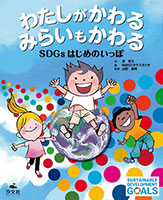
「初のSDGs絵本」の意図するところ
原 琴乃 作/MAKOオケスタジオ 絵/山田基靖 監修
2020年5月刊行
この本は、SDGsが国連で採択された頃から外務省でその旗振り役を担ってきた、著者の原琴乃さんの想いを形にしたものです。
SDGsは2030年に向けて様々な社会問題を解決するための指針となるものなので、未来の担い手である子どもたちに理解してもらわぬことには、目標が達成できません。ところが、財界を中心に大人の世界では少しずつ認知されつつありましたが、子どもにそのメッセージを届けることに、長年苦戦している状況でした。そこで、絵本の形で伝えることを提案したのです。
SDGsに関する児童書は、企画当時も存在していたのですが、いずれも17の目標を紹介することに重きを置くものでした。低年齢の子など、もっと広く子どもたちに理解してもらうためには、SDGsのベースとなる考え方を、感覚的に理解してもらえるようなものをつくることが必要なのではとの話になり、そのための表現方法を考えました。
現在、SDGsという言葉は、テレビなどで取り上げられるようになったこともあり、広く浸透しつつありますが、環境問題の延長の言葉、というような扱いを受けることがほとんどです。この絵本では、環境問題は世界の諸問題のひとつに過ぎないこと。「つながり」というキーワードのもと、多くの問題解決に向けたひとりひとりの行動を結びつけることが大事であること。そして、それらを広げることで、「ひとりも取り残されない世の中」をつくることが大切であることを伝えています。結果的に、SDGsの本質を理解するために最適との評価をいただき、多くの自治体などで副教材的に広めていただいています。さらにありがたいことに、大人が読んでも意味があると、様々なところでSDGsの啓蒙活動の際にご活用いただいています。
SDGsは国連での採択後、政府を経由して国内の人々にその理念がもたらされました。私たち子どもの本に関わる者たちは、ときに政府見解に異を唱えることが求められる立場です。しかしながら、このSDGsの理念は、政府にとっても、子どもの未来を預かる私たちにとっても、どちらにも有益なもの。課題に向けてすべての立場の人が、手と手をとって進むために役立てることができるものです。
平和の希求を目的に、学校図書館や公共図書館を中心に児童書の普及を担ってきた汐文社からこの本を発刊することに大きな意義があるのではと考えています。
この本が、よりよい世の中を形成するためのあらたな議論のきっかけになればと思っています。