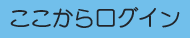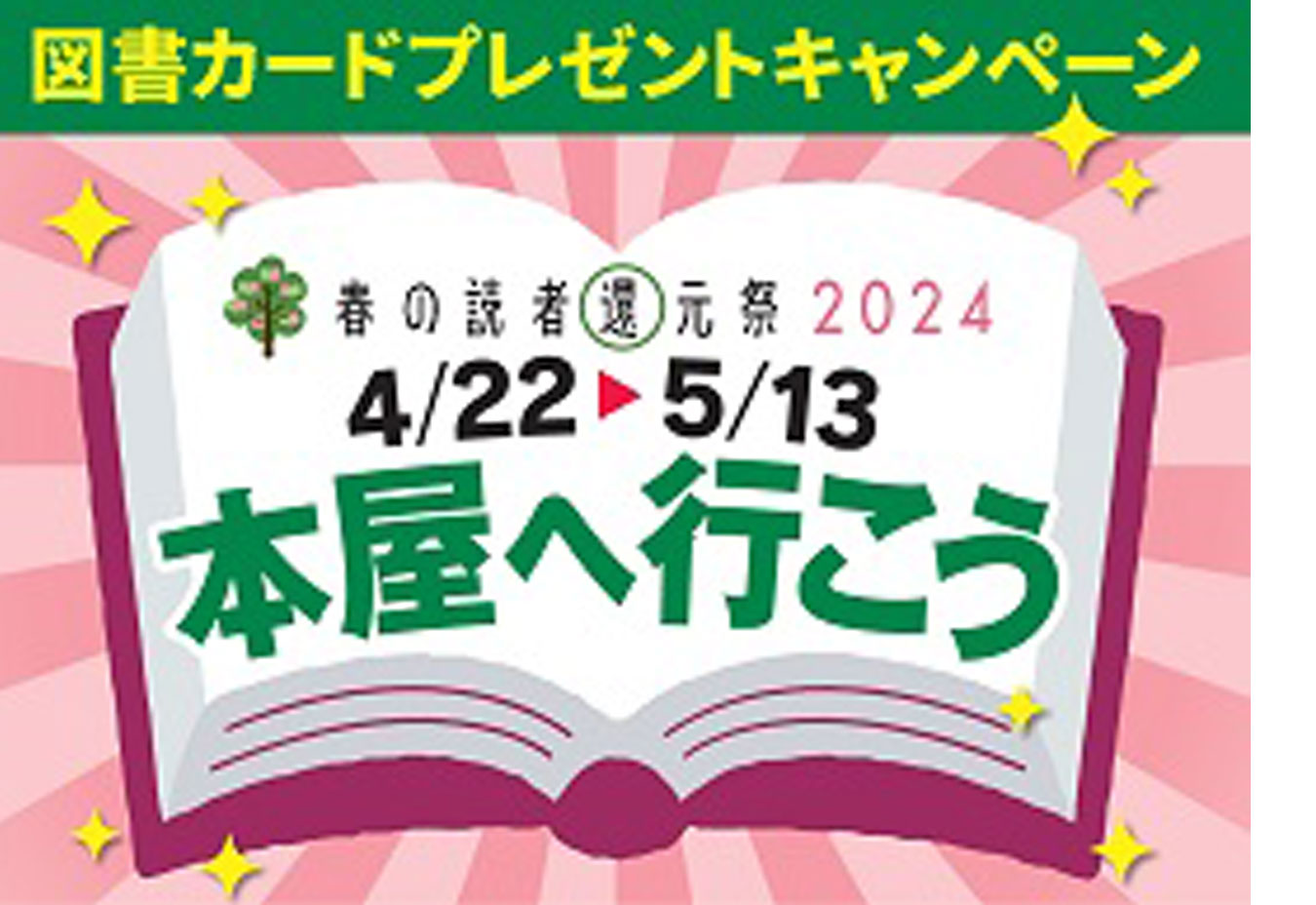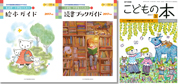子どもの心に沁み込む、人間関係の極意
齋藤 孝 著
2020年8月刊行
小学校低学年までは、一緒に遊べたらもう友だち。何か話すきっかけがあるだけですぐに仲良くなれます。ところが小学校高学年から中学生あたりになると、友だちに関する悩みが増えてきます。「どこまで本音を言っていいんだろう?」「一人きりになりたいときもあるんだけど、こんな気持ちは変なのかな?」
この本は、そんな悩みをもつ中高生に向けて明治大学教授・齋藤孝先生が書いた友だち関係の処方箋ともいえる本です。
中学生ぐらいになると、親には相談しづらいことも増えてきます。しかも、親たちが中高生だったときと現代とでは、環境が全然違います。SNSの浸透や、性や性別に対する意識、いじめの定義なども大きく変わりました。
いまの子どもたちの悩みを、正直、親たちは肌感覚として理解ができません。それがわかっているから、子どもたちはもっとも辛い、もっとも深刻な悩みを親に打ち明けないのです。
時代の流れが加速度的に速くなっている現代の子どもたちは、こうして悩みを抱え込んでいくのだと思います。
しかし友だち関係は人間関係。なにか普遍的な考え方や方法論はないのでしょうか?
その疑問に明快に答えてくれたのが、齋藤孝先生です。齋藤先生は、「雑談力」や「読書術」などで有名ですが、じつは明治大学で教育学を教える、いわば「先生の先生」。つまり、「学校の先生になりたい」という大学生と常に接し、彼らと議論を重ね、子どもたちとのコミュニケーションを考え続けているわけです。
本書の中で齋藤先生は、「中学生から高校生にかけての時期には、『友だちが必要』というよりも、『友だちをつくろうとする行為、行動』が必要」と説きます。
友だち関係は、面倒くさいこともあるし、イヤなことも起きる。それでも「必要」と言い切るのは、「自分以外のほかの人とどうやって関係を結び、どうやって共存していくか、(中略)友だちづきあいを通じて、社会を生き抜いていくために身につけておきたい人間関係の練習」だからだと言うのです。
練習なら、間違ってもいい。むしろ間違えることで成長できます。本書は、人間関係のいろいろなメソッドや哲学を紹介していますが、極意は、じつはここなのだと思います。
「友だち関係は、将来の人間関係の練習。だから怖がらなくていいよ」
親がそう言っても響かないことも多いですが、本に書かれていると不思議と子どもの心に沁み込んできます。この本を読んで、学校生活や友だち関係に悩んでいた中高生が、少しでも前向きになってくれたらうれしいです。