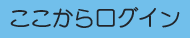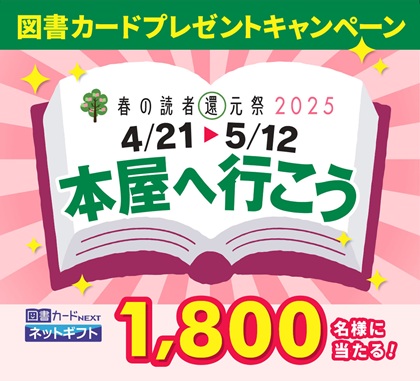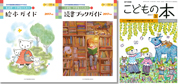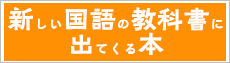俯瞰の視点
私は普段イラストレーターとして仕事をしているのですが、絵本(自著)は本作を入れて3作目になります。絵本作家としては、まだまだ子どもみたいなものです。
一からお話を考え、絵本を紡ぐことは楽しい作業ですが、なかなか難しいものでもあります。考えて、描いて、直して、また考えて、というのを繰り返します。なかなかうまくいきません。まるで、今回の絵本『じてんしゃのれるかな』の中の「ぼく」のようです。
「ぼく」に「だれか」が話しかけます。
「へいきへいき」
「バランスバランス」
「リズムリズム」
「おちついておちついて」
「つよくつよく」。
それまで、できない道を堂々巡りしている「ぼく」をうまく軌道修正してくれます。そして最後は「ぼく」自身の気づきによって、見事自転車に乗れるようになります。
自転車に限らず、できないことができるようになるにはどうすればよいだろう、という思いは皆が抱く気持ちだと思います。子どもによっては自然にスイスイできてしまう場合もあるでしょう。でも大抵そううまくはいきません。付かず離れず、常に一定の距離で冷静に全体を見ていてくれる「だれか」の存在、俯瞰の視点が必要だと思います。親や学校の先生、近所のおばさん、親戚のおじさん、などなど、子どもを取り巻くすべての社会に、この俯瞰の視点が、たくさんあってほしいな、と思います。
この絵本の中の「ぼく」の「おとうさん」は俯瞰の視点を持っていません。私には子どもがいますが、我が子に対して私自身俯瞰の視点を持てているだろうか、と考えます。さらに子どもの頃の私にとってそれが誰だったか、いろいろ思い出します。
そして俯瞰の視点は子どもだけでなく、大人にとっても必要なものだと思います。実際、絵本作家として子ども同然の私が絵本を完成させることができたのも、その存在があったからです。
(ひらた・としゆき)●既刊に『やじるし』『ぼくのぼうし』、絵を担当した『つみき』(中川ひろたか/文)など。

あかね書房
『じてんしゃのれるかな』
平田利之・作
本体1、200円